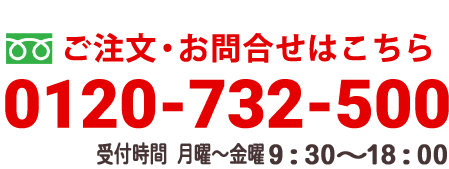さつまいもは焼き方によって甘みが変化する!?
2019.10.30
みなさんは秋といえばどんな食べ物を思い浮かべますか。
「「 さつまいも 」」
甘くて美味しいですよね。焼き芋にしてもよし!スイーツにしてもよし!今回は秋に食べたくなる「さつまいも」のあれこれについて紹介します。
■ さつまいもの基本情報
さつまいもは熱帯原産であり、暖かい地域では季節関係なく常に栽培されます。日本などの温帯地域では春につるを挿し、秋に収穫します。熱帯地域の芋であるさつまいもは低温環境下に耐性がありません。そのため、10℃以下である冷蔵庫に入れてしまうと低温障害を引き起こし、腐りやすくなってしまいます。
さつまいもの最適な保管環境は、温度12~15℃、湿度85~90%です。今の時期ですと、冷暗所に常温で保管するとよいでしょう。
さつまいもの主成分はでんぷんで、ビタミンC、B1、B6などを豊富に含んでいます。安納芋などのオレンジ色の品種では緑黄色野菜と同等のカロテンを含んでいます。また、切るとでてくる白い液は「ヤラピン」といい、腸の蠕動運動を促進させてくれます。
そして、さつまいもは芋類の中では唯一強い甘味をもっています。それによって品種も色々とありますよね。次はさつまいもの種類について紹介します。
■ さつまいもの種類
さつまいもは色や粘性などが異なる品種が多くあります。例えば、鳴門金時、安納芋、紅あずまなどなど…
〇鳴門金時
徳島県で有名なお芋です。
〇安納芋
種子島特産のお芋です。オレンジ色の果肉にはカロテンが含まれています。甘みが強くねっとりしています。
〇紅あずま
関東地方代表の品種です。鮮やかな黄色で加熱すると甘みが増すので、焼き芋にするには最適です。
■ 焼き方によって変わるさつまいもの甘さ
外で食べる石焼きいもってなんであんなに甘くて美味しいのでしょうかね…逆に電子レンジで加熱したさつまいもはなんだか甘くないなと感じたことはありませんか。お芋の種類にもよりますが、実は加熱方法によっても差が出てくるのです。
さつまいもには「β-アミラーゼ」というでんぷんの消化酵素が多く含まれています。
このβ-アミラーゼが活性化する温度まで、ゆっくりと低温で加熱することでその間にβ-アミラーゼがでんぷんを糖化し、甘みが増大します。
そのため、焼き芋を甘く美味しく食べるには、β-アミラーゼが働く最適温度帯である50~55℃、70℃前後を維持し加熱できるとより甘い焼き芋が完成します。
短時間で高温に達する電子レンジ加熱では、でんぷんが糊化した時点でβ-アミラーゼが失活するため、甘みの増加は少ないです。
※糊化…でんぷんを水と加熱することで、でんぷんが糊状になることを言います。例えば、米粒を炊いてふっくら炊きたてのごはんができた状態をでんぷんが糊化している状態といいます。
石焼きいもはなぜか美味しいというわけではなく、このような理由があるため甘みが強く美味しいのです。
<自宅でのお勧め加熱方法>
50~70℃前後の低温で30分加熱すると良いでしょう。
電子レンジであればできるだけ低いワット数で加熱、オーブンではアルミホイルなどで包んで加熱するなど低温でじっくりというのを心掛けましょう!
料理で使う場合も薄切りで使うより、厚切りの方が甘みを感じられる料理ができます。ぜひ試してみてください♪
最後に、血糖値が気になる…という方のために食べ方の工夫をお伝えします。
■ 糖質が気になる…という方
美味しく食べたいといっても糖質が気になりますよね。しかし、さつまいもは食物繊維が豊富なお芋ですので、意外にも血糖上昇のスピードを示すGI値は低めなのですよ。それでもやっぱり気になるという方のために、血糖値に配慮した食べ方を紹介します。
<さつまいもの糖質が気になる方の食べ方>
・皮ごと食べる
皮には食物繊維やビタミンC、ミネラルなどが含まれています。
・冷やして食べる
糊化したでんぷんが冷えると食物繊維と似たようなはたらきをするため、血糖の上昇をゆるやかにすることができます。冷ごはんがいい!と言われているのと同じ理由ですね。
情報提供元:メディカルフードサービス 管理栄養士