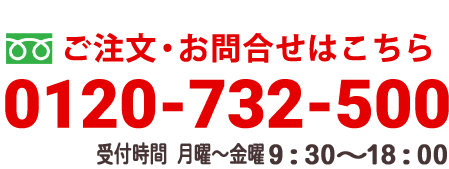りんごと梨の栄養を比較!栄養や効能の違いは何?
2020.09.10
秋といえば甘く熟した「果物」が食べたくなりますよね。今回は秋の果物の代表格「りんご」と「梨」について解説していきます。
学名分類ではどちらもバラ科。りんごの旬は9月~11月、梨の旬は9~10月で、梨の方が旬をむかえる時期が早いのですが、栄養的にはどのような違いがあるのでしょうか。
りんごと梨の栄養価を比較!
代表的な栄養価の数値の違いを紹介します。
りんご 100gあたりの栄養価
【りんご】

エネルギー:54kcal
水分:84.9g
タンパク質:0.2g
脂質:0.1g
炭水化物:14.6g
(糖質:13.1g)
カリウム:110mg
カルシウム:3mg
マグネシウム:3mg
リン:10mg
ビタミンC:4mg
食物繊維:1.5g
梨 100gあたりの栄養価
【梨】

エネルギー:43kcal
水分:88.0g
タンパク質:0.3g
脂質:0.1g
炭水化物:11.3g
(糖質:10.4g)
カリウム:140mg
カルシウム:2mg
マグネシウム:5mg
リン:11mg
ビタミンC:3mg
食物繊維:0.9g
エネルギーが低いのは、梨ですので、ダイエットで少しでもエネルギーを減らしたい場合にはりんごよりも梨の方が良いでしょう。また、糖質の量に関しても梨の方が若干少なめです。
ただどちらも100gあたりに10g以上の糖質を含むため、糖質制限中の方は要注意な食品です。
りんごと梨の栄養とその効能を比較!
代表的な栄養価の違いを確認しましたが、食べることによって期待できる効能の違いもみていきましょう。
りんご の栄養とその効能
りんごはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富です。
- 整腸作用とコレステロールの吸収を阻害する
りんごに含まれる水溶性食物繊維のペクチンには整腸作用、コレステロールの吸収を阻害させる効能があります。
また、不溶性食物繊維のレグナンやセルロースには腸の蠕動運動を活発化させ、排便をサポート、コレステロールの吸収を阻害する効能があります。
- 有機酸で疲労回復
りんごの酸味のもとのリンゴ酸やクエン酸などの有機酸には疲労回復効果があります。
- 抗酸化作用
ポリフェノールのプロシアニジンはカテキンの結合体で果肉に、アントシアニンは赤い皮に含まれており、老化や動脈硬化等を予防する抗酸化作用があります。
ポリフェノール類は皮に多く含まれているので、皮ごと食べることで栄養を多く摂ることができます。
梨の栄養とその効能
梨はほどよい甘みとみずみずしさが特徴。みずみずしさから想像できる通り、梨の9割は水分でできています。
- 高血圧予防
梨はカリウムを比較的多く含みます。カリウムは利尿作用もあり体内の塩分を排出するのでむくみ解消やデトックス効果が期待できます。
- 夏場の疲労回復
水分が多く含まれる梨は、夏場に汗をかいて失った水分やカリウムなどのミネラル類を補給するのに最適!
また、梨に豊富に含まれるアスパラギン酸には疲労回復効果があり、水分とともに栄養補給ができます。
- 整腸作用
梨には清涼感のある甘さをもつソルビトールという糖アルコールが含まれています。
ソルビトールには整腸作用があり、糖類の中でも低カロリーという特徴があります。
- 消化を促進
タンパク質分解酵素である「プロテアーゼ」を含んでいます。プロテアーゼは消化を促進するほかに、お肉などをやわらかくする働きがあるため、すりおろした梨をお肉などと合わせることでお肉料理はやわらかく仕上げることができます。
焼き肉のたれなどに少しすりおろしてお肉を漬け込むとやわらかく美味しく仕上がりますよ。
さて、いかがでしたでしょうか。似ているようで異なる栄養をもつりんごと梨。どちらを食べようか迷ったときは「栄養」に着目して決めてみるのもいいかもしれません。
情報提供元:メディカルフードサービス 管理栄養士