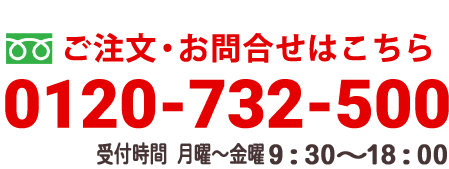減塩表示の落とし穴!その表示、本当に減塩?
2021.03.29
食品のパッケージなどの食品表示を見ると、うす塩、うす塩味、塩味控えめ、塩分ひかえめ、減塩、食塩無添加、無塩・・・などいろいろな表現がありませんか。
どれも塩分が同じだけ少ないわけではなく、表現方法によって塩分量は異なるのです。この中には、減塩されていなくても表示できる表現もあるのですよ!
減塩表示といっても色々
塩分が少ない、いわゆる「減塩商品」。塩分ひかえめ、減塩、食塩無添加、無塩等色々な表現があります。この表現、一見するとどれも同じくらい「減塩」になっているのではないかと感じられますが、表示内容によって塩分がどのくらい減っているのかは異なるのです。
「減塩表示」は、塩分が低減された度合いによって3つに分けられます。これら表示のことを栄養強調表示といいます。
栄養強調表示1:低い旨の表示
「低ナトリウム」「低塩」「塩分控えめ」「うす塩」
→ナトリウムが食品100gあたり、120mg以下(食塩相当量0.3g以下)
栄養強調表示2:低減された旨の表示
「〇%減塩」「食塩〇%カット」
→ナトリウムが食品100gあたり、120mg以上(食塩相当量0.3g以下)減少していること
※醤油のナトリウムについて表示する場合は、標準的な醤油に比べて低減割合が20%以上であること
※他の食品と比べて、どのくらい減らされているのか、低減された旨の表示が必要
栄養強調表示3:含まない旨の表示
「無塩」「ナトリウムレス」「塩分ゼロ」
→ナトリウムが食品100gあたり5mgに満たないこと
「低ナトリウム」「低塩」「塩分控えめ」という表示が可能なのは、食品100g中ナトリウムが120mg以下(食塩相当量 約0.3g以下)と定められています。
また、従来品と比較して100g中ナトリウムが120mg(食塩相当量 約0.3g)以上少ないものに「○○%減塩」、「塩分○○%カット」などの割合を伴う表現で「減塩」の表示でき、元々塩分が多い食品に多く付けられています。
「食塩不使用」の表示はホントなの?
「減塩表示」以外にも注意したい表示について紹介します。
「食塩不使用」「塩分無添加」などの表示を見るとあなたならどう解釈しますか?
「含まない旨」の表示と同じく、ナトリウムが食品100gあたり5mgに満たないことと同じなのではないか勘違いしやすい表現となっています。「○○無添加」「○○不使用」は、「添加していない旨の表示」となり、無添加について強調したいときに使う「無添加強調表示」なのです。そのため、「食塩不使用」「塩分無添加」とは食品加工時に食塩を追加していないということで、素材そのものに含まれる食塩やナトリウムは入っており、塩分が全く含まれていないという意味ではないので注意が必要です。
ポテトチップの「うす塩味」も減塩!?
ポテトチップや梅干しなどに書かれていることの多い「うす塩味」や「塩味控えめ」という表示。減塩されていると思って購入していませんか?
「うす塩“味”」、「塩“味”控えめ」などの表示は味覚に対する表現で、「塩味が少なくなるように味付けをしています」というアピールなのです。味の表現であるため、実際の塩分量は問われません。いくら塩分量が多くても「うす塩味」と書くことができてしまうので注意が必要です。
さていかがでしたでしょうか。あなたが普段、「減塩だ!」と思って選んでいる商品は本当に塩分が少なくなっていますか?表示だけを鵜呑みにせず、食塩相当量やナトリウム量が記載されている栄養成分表示までしっかりと見ることが大切です。